ピタゴラス B.C.550年頃前提事項: 最初の哲学者タレス
「神話」という迷信から開放された人類は、ようやく自分の頭で 「世界とは何か?万物の根源は何か?」という問題を考えるようになった。 そして、最初の哲学者タレスは、自然への観察から「万物のもとは水だ」と考えた。 だが、多種多様な世界において「水がすべてだ」と考えるのは、説得力がない。 そこで、タレス以後の哲学者たちは、タレスの説を否定し、 「万物の根源は、無限定な何かだ」アナクシマンドロス(タレスの弟子) 「万物は、空気(気息)が固まってできたのだ」アナクシメネス(タレスの弟子の弟子) と色々なことを考え出したのだが、 あまり説得力のない点では、タレスと大差なかった。 しかし、B.C.550年頃。 説得力を持って、世界の根源を説明しようとする人物が現れる。 ピタゴラスである。 「万物の根源は、数である」 とピタゴラスは高らかに宣言した。 ピタゴラスは、自然現象が一定の法則に支配されていること、 そして、その法則が数式により表せることに気がついたのだ。 たとえば、楽器の弦を調律する道具を発明したのはピタゴラスとされている。 それまでは、演奏者が耳で、良い音を探して調律していた時代に、 弦の長さの整数比によって、和音が奏でられることを発見し、 音楽に大きく貢献したのである。 このように、音楽の和音から、惑星の軌道にいたるまで、 あらゆる事柄の背後に「数の秩序」が潜んでいることに気づいたピタゴラスは、 その「数」の美しさに陶酔してしまい、 ついには「数」を崇める宗教として、ピタゴラス教団を設立するのである。 そこでは、大勢の弟子たちが、「数を知ることが真理に近づくこと」だと信じ、 日夜、数学の証明に励んでいた。 (ちなみに、教団に入るためには、全財産を寄付し、俗世を断つ必要がある) その中で生まれた「ピタゴラスの定理」こと「三平方の定理」は 「直角三角形の斜辺の2乗は、他の2辺の2乗の和と等しい」 という直角三角形の3辺の関係を示したものだ。 |
|
関連事項: ヘラクレイトス(1)
|
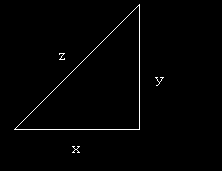 X2 + Y2 = Z2
この計算方法は、古くは中国にもあったものだが、それは経験的なものであり、
数学的な手法を使って、それが成り立つことをきちんと証明したのは
ピタゴラス(教団)が初めてだった。
ところで、ピタゴラス教団が、
「数」と考えていたのは、整数と整数比(分数)のみであった。
整数 ={ 1, 2, 3, 4, 5, ... , n }
分数 ={ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ..., 2/3, 2/4, 2/5,...., n/m }
「この世界は、整数とその比(分数)によって、秩序をもって成り立っている」
とピタゴラス教団は教える。
しかし、ちょっと待って欲しい。
「ピタゴラスの定理」を用いれば、
整数でも分数でもない「無理数」が出てくるときもある。
12 + 12 = Z2
Z = √2 (無理数)
この整数でも分数でもない「無理数」という存在があることを
弟子の一人が「ピタゴラスの定理」を使って、証明してしまったから、さあ大変。
「あれれ、教祖様? X=1、Y=1のとき、
Z って、『整数でも分数でもない 変な数』になっちゃいませんか?」
ピタゴラスは大変なショックを受けた。
まさに開いた口が塞がらなかっただろう。
教団の教えと反する事を、自らの定理で証明してしまったのだから。
ピタゴラスは、その弟子を殺害し、教団の教えを否定する無理数の存在を
「決して云ってはならない秘密」として隠してしまったのであった。
ちなみに、このピタゴラス教団。
最後は、徹底した秘密主義とエリート意識から、市民の反感を買って、
弟子たちは教団の施設もろとも焼き殺され、
ピタゴラス自身は、市民からリンチを受けて死んでしまうのであった。
ともかく。
ピタゴラスは、自然現象の背後に数学的な法則が内在していることに気がつき、
万物の根源として、初めて数学という「観念的な存在」を導入したことにより、
以後の哲学に大きな影響を与えるのである。
X2 + Y2 = Z2
この計算方法は、古くは中国にもあったものだが、それは経験的なものであり、
数学的な手法を使って、それが成り立つことをきちんと証明したのは
ピタゴラス(教団)が初めてだった。
ところで、ピタゴラス教団が、
「数」と考えていたのは、整数と整数比(分数)のみであった。
整数 ={ 1, 2, 3, 4, 5, ... , n }
分数 ={ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ..., 2/3, 2/4, 2/5,...., n/m }
「この世界は、整数とその比(分数)によって、秩序をもって成り立っている」
とピタゴラス教団は教える。
しかし、ちょっと待って欲しい。
「ピタゴラスの定理」を用いれば、
整数でも分数でもない「無理数」が出てくるときもある。
12 + 12 = Z2
Z = √2 (無理数)
この整数でも分数でもない「無理数」という存在があることを
弟子の一人が「ピタゴラスの定理」を使って、証明してしまったから、さあ大変。
「あれれ、教祖様? X=1、Y=1のとき、
Z って、『整数でも分数でもない 変な数』になっちゃいませんか?」
ピタゴラスは大変なショックを受けた。
まさに開いた口が塞がらなかっただろう。
教団の教えと反する事を、自らの定理で証明してしまったのだから。
ピタゴラスは、その弟子を殺害し、教団の教えを否定する無理数の存在を
「決して云ってはならない秘密」として隠してしまったのであった。
ちなみに、このピタゴラス教団。
最後は、徹底した秘密主義とエリート意識から、市民の反感を買って、
弟子たちは教団の施設もろとも焼き殺され、
ピタゴラス自身は、市民からリンチを受けて死んでしまうのであった。
ともかく。
ピタゴラスは、自然現象の背後に数学的な法則が内在していることに気がつき、
万物の根源として、初めて数学という「観念的な存在」を導入したことにより、
以後の哲学に大きな影響を与えるのである。